 エネラボ所長
エネラボ所長難しい用語は、すべて覚える必要はありません。でも、この記事があれば、いつでも安心して確認できます。
蓄電池を検討していると、「全負荷」「SOC」「サイクル数」といった専門用語を目にする機会があります。しかし、たくさんの用語を一度に覚えるのは大変ですし、そもそもすべてを知る必要はありません。
この記事は、そんなあなたのための「蓄電池の専門用語ガイド」です。
気になる用語が出てきた時に、このページを開いて確認すれば、一つひとつの言葉の意味を噛み砕いて理解できます。そして、なぜその用語が重要なのかを知ることで、あなたは自信をもって業者と話し、自分にぴったりの蓄電池を納得して選べるようになるでしょう。
蓄電池の「タイプ」に関する用語


蓄電池システムは、核となるパワーコンディショナーの方式によって「単機能型」と「ハイブリッド型」の2つのタイプに分かれます。このパワーコンディショナは、太陽光で発電した電気を家庭で使えるように変換したり、蓄電池に貯めたりする、いわば「変換器」の役割を担っています。ここでは、それぞれの特徴を解説していきます。
単機能型
- 解説
- 太陽光発電システムとは独立したパワーコンディショナを持つ蓄電池です。太陽光発電用と蓄電池用で、それぞれ別の変換器を設置する必要があります。
- 太陽光発電システムとは独立したパワーコンディショナを持つ蓄電池です。太陽光発電用と蓄電池用で、それぞれ別の変換器を設置する必要があります。
- なぜ知っておくべきか
- すでに太陽光発電を設置済みのご家庭が、後から蓄電池を追加したい場合の選択肢となります。ハイブリッド型よりも導入コストを抑えやすいメリットがあります。
ハイブリッド型
- 解説
- 太陽光発電と蓄電池のパワーコンディショナを一つにまとめたタイプの蓄電池です。電気の変換が一度で済むため、単機能型よりも変換ロスが少なく、効率が良いのが特徴です。
- 太陽光発電と蓄電池のパワーコンディショナを一つにまとめたタイプの蓄電池です。電気の変換が一度で済むため、単機能型よりも変換ロスが少なく、効率が良いのが特徴です。
- なぜ知っておくべきか
- これから太陽光発電と蓄電池をセットで導入したいと考える方にとって、現在の主流となるタイプです。また、既存の太陽光発電を設置してからある程度の年数が経過しているご家庭にとっても、買い替えのタイミングでパワーコンディショナを一本化できるため、効率の面でも設置スペースの面でもメリットが大きい選択肢となります。
「非常時の使い方」に関する用語


ここでは、災害などで停電が起きた際に、蓄電池からどこに電気を送るかを決める「全負荷」と「特定負荷」について解説します。
通常時(太陽光で発電した電気を貯めたり、蓄電池の電気を使ったりする時)は、全負荷・特定負荷に関係なく、蓄電池の電気を家全体で利用できます。全負荷と特定負荷の違いが出るのは、あくまで停電時のみです。
全負荷(ぜんふか)
- 解説
- 停電時に、家の中にあるすべての電化製品をバックアップできるタイプの蓄電池です。エアコンやIHクッキングヒーター、200V機器など、消費電力の大きな製品も普段と変わらず使用できます。
- 停電時に、家の中にあるすべての電化製品をバックアップできるタイプの蓄電池です。エアコンやIHクッキングヒーター、200V機器など、消費電力の大きな製品も普段と変わらず使用できます。
- なぜ知っておくべきか
- 災害時でも、普段と全く同じように生活を送りたいと考える方にとって、最も安心感が高い選択肢になります。ただし、その分、機器の価格は高くなり、蓄電容量も大きくなりがちです。
特定負荷(とくていふか)
- 解説
- 停電時に、事前に指定した一部の電化製品や部屋だけをバックアップできるタイプの蓄電池です。例えば、リビングの照明や冷蔵庫、携帯電話の充電用コンセントなど、必要最低限の場所のみに電力を供給します。
- 停電時に、事前に指定した一部の電化製品や部屋だけをバックアップできるタイプの蓄電池です。例えば、リビングの照明や冷蔵庫、携帯電話の充電用コンセントなど、必要最低限の場所のみに電力を供給します。
- なぜ知っておくべきか
- 災害時に最低限の生活を確保できれば十分と考える方にとって、費用を抑えやすい選択肢になります。全負荷型に比べて機器の価格が安く、蓄電容量も小さくて済むため、導入のハードルが下がります。
「性能・寿命」に関する用語


ここでは、蓄電池を選ぶ上で特に重要となる、製品の性能や寿命に関連する用語を解説します。これらの用語を知っておくことで、カタログの数字を正しく読み解き、あなたの家に合った製品を見極めることができます。
蓄電容量
- 解説
- 蓄電池が電気をどれだけ溜められるかを示す数値です。この容量が大きければ大きいほど、より多くの電気を貯めることができます。
- 蓄電池が電気をどれだけ溜められるかを示す数値です。この容量が大きければ大きいほど、より多くの電気を貯めることができます。
- なぜ知っておくべきか
- ご家庭の電気使用量や災害時の備えなど、あなたのライフスタイルに合った容量を選ぶ際の最も重要な指標となるためです。蓄電容量が少なすぎると、停電時に必要な電力が賄えなくなる可能性があります。
サイクル数
- 解説
- 蓄電池の「満充電から放電して使い切る」というサイクルを何回繰り返せるかを示した指標で、製品の寿命の目安となる数値です。充電と放電で1セットと考え、例えば、バッテリー残量が0%から100%まで充電され、再び0%になるまで使い切ることで「1回(1サイクル)」と数えます。
- 蓄電池の「満充電から放電して使い切る」というサイクルを何回繰り返せるかを示した指標で、製品の寿命の目安となる数値です。充電と放電で1セットと考え、例えば、バッテリー残量が0%から100%まで充電され、再び0%になるまで使い切ることで「1回(1サイクル)」と数えます。
- なぜ知っておくべきか
- 蓄電池の製品寿命は、保証期間とともに、このサイクル数が一つの重要な指標となります。製品によってサイクル数が異なるため、長期的な視点で比較検討する際に役立ちます。
SOC(State of Charge)
- 解説
- 蓄電池の残量(充電率)を指す言葉です。スマートフォンやノートパソコンのバッテリー残量表示と同じもので、満充電を100%、完全に放電された状態を0%と表記します。たとえば、半分電気を使った状態であれば、SOCは50%となります。
- 蓄電池の残量(充電率)を指す言葉です。スマートフォンやノートパソコンのバッテリー残量表示と同じもので、満充電を100%、完全に放電された状態を0%と表記します。たとえば、半分電気を使った状態であれば、SOCは50%となります。
- なぜ知っておくべきか
- 蓄電池を効率的に運用し、寿命を延ばすために非常に重要な指標です。多くの蓄電池は、SOCの「下限」と「上限」を設定できます。
- SOC下限:指定した残量(例:20%)になると放電を停止し、蓄電池の使い切りを防ぎます。これにより、災害時に備えて最低限の電力を確保できます。
- SOC上限:指定した残量(例:80%)を超えて充電しないようにします。これにより、バッテリーの劣化を抑え、寿命を延ばすことにつながります。
- SOC下限:指定した残量(例:20%)になると放電を停止し、蓄電池の使い切りを防ぎます。これにより、災害時に備えて最低限の電力を確保できます。
- 蓄電池を効率的に運用し、寿命を延ばすために非常に重要な指標です。多くの蓄電池は、SOCの「下限」と「上限」を設定できます。
放電深度(DoD: Depth of Discharge)
- 解説
- バッテリーをどのくらい使い切るかの割合を示す言葉です。たとえば、10kWhの蓄電池で3kWh使用した場合、残量が7kWhなので放電深度は30%となります。バッテリーをすべて使い切る場合は「放電深度100%」と表記されます。
- バッテリーをどのくらい使い切るかの割合を示す言葉です。たとえば、10kWhの蓄電池で3kWh使用した場合、残量が7kWhなので放電深度は30%となります。バッテリーをすべて使い切る場合は「放電深度100%」と表記されます。
- なぜ知っておくべきか
- サイクル数と同様、この放電深度も蓄電池の寿命に大きく影響します。一般的に、放電深度が浅い(使い切りすぎない)ほど、サイクル数が増え、寿命が長くなる傾向にあります。例えば100%→0%→100%と毎回使い切るより、100%⇒40%⇒100%⇒60%…と使ったほうが寿命が長くなります。
まとめ
蓄電池の導入を検討する上で、たくさんの専門用語に戸惑うかもしれません。しかし、この記事を通して、難しい用語をすべて暗記する必要はないと感じていただけたのではないでしょうか。
大切なのは、各用語が持つ本当の意味と、それが「あなたの家の使い方」や「蓄電池の寿命」にどう影響するのかを理解することです。
用語の意味を把握しておくことで、カタログの数字を鵜呑みにせず、業者の説明をより深く理解できます。そして、疑問に思ったことを自信を持って質問できるようになるでしょう。
この記事が、あなたの蓄電池選びを成功させるための心強いガイドとなり、後悔のない決断に繋がることを願っています。
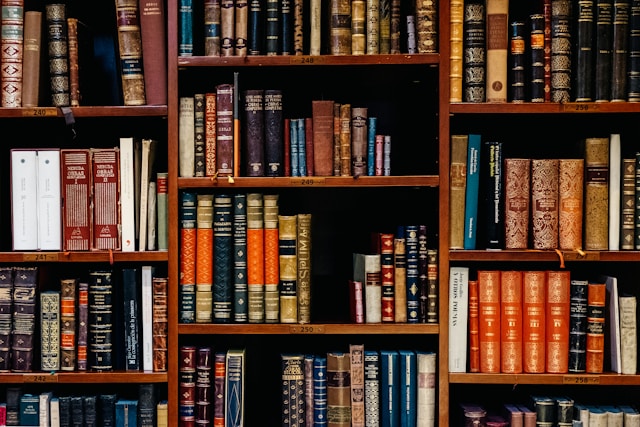




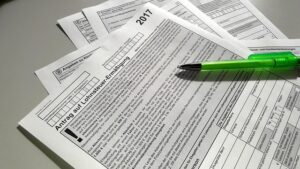



コメント